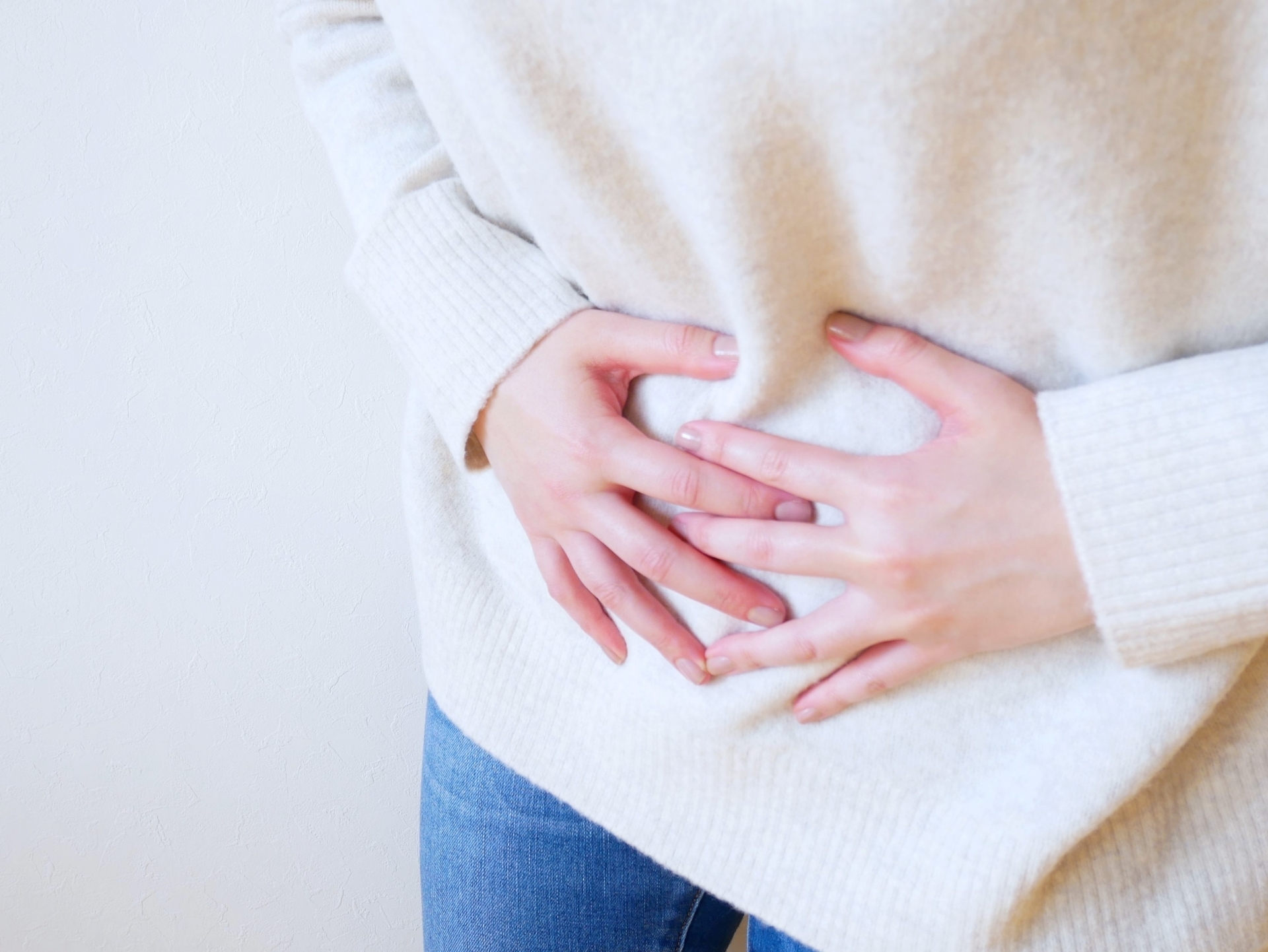
機能性ディスペプシア(Functional Dyspepsia、FD)は、胃の痛みや不快感、食後の膨満感、早期満腹感などの症状が続く病気ですが、検査をしても明確な異常が見つからないのが特徴です。
原因はストレスや自律神経の乱れ、胃の運動機能の低下などが関係していると考えられています。そこで注目されているのが「鍼灸」と「機能神経学」です。
これらがなぜ有効なのか、わかりやすく解説します。
機能性ディスペプシアと鍼灸治療
まず「鍼灸」について。鍼灸は、体の特定のツボに鍼やお灸を用いて刺激を与えることで、身体のバランスを整える伝統的な東洋医学の方法です。
鍼灸によって自律神経の働きを整えることができます。自律神経は、胃の動きや胃酸の分泌などをコントロールしており、これが乱れるとFDのような症状が出やすくなります。
鍼灸治療では、交感神経と副交感神経のバランスをとることで、胃腸の働きを正常化し、胃の不快な症状をやわらげることができます。
次に「機能神経学」とは、脳や神経の働きを科学的に評価し、非薬物的な方法で神経機能を改善する療法です。ストレスや生活習慣の影響で脳と内臓のつながりがうまくいかなくなると、胃の感受性が高まり、わずかな刺激でも胃の不快感を感じやすくなります。
機能神経学では、視覚・前庭(バランス)・感覚刺激などを用いて脳の神経回路を活性化し、自律神経や内臓機能の調整を促すことで、FDの症状の軽減を目指せます。
つまり、鍼灸と機能神経学はいずれも「体の内側から調整する」方法であり、薬に頼らずに自然な回復力を高める点で共通しています。
FDは心理的な要素も大きいため、身体だけでなく心のバランスも整えるこれらのアプローチが効果的とされているのです。
参考文献:Tack J, Talley NJ. Functional dyspepsia — symptoms, definitions and validity of the Rome III criteria. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2013.
長尾和宏『自律神経を整える習慣』(青春出版社)







